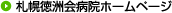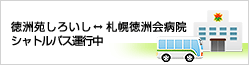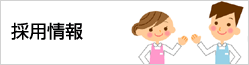居宅介護支援事業所
読書の秋
高齢者との面談の際に「ながく生きることはつらい」、「どうして長生きして、しまったのだろう」などと話される場面によく遭遇します。
少し前までは「太平洋戦争が終わってから平成にかけて協力はしたことはあるけど実際に国内で戦争が起きなかったので、安心して健康でいられた証拠ではないですか」など騙しだましの返答でなんとなく相手を納得させていたのですが、それも時代が変わり戦後生まれの世代には通用しなくなってきています。
不真面目で本人と面と向かって面談に向き合っていなかった“つけ”が最近来ている感じでした。
少し話は変わりますが、みすず書房から新版として出ているヴィクトール・E・フランクルという方が書いた『夜と霧』(池田香代子 訳)を先日読み終わりました。
インターネットで「おすすめの本」として出ていたので興味本位で注文。
本の裏表紙に作者の顔写真と数行の本文を掲載していましたが、こんな文章が書かれていました。
『わたしたちは、おそらくこれまでのどの時代の人間も知らなかった『人間』を知った。では、この人間とはなにものか。人間とは何かを常に決定する存在だ。人間とは、ガス室を発明した存在だ。しかし同時に、ガス室に入っても毅然として祈りの言葉を口にする存在でもあった』
この数行の文章の強さや重みを感じながら本書を読み始めました。
精神医学を学んでいた作者が戦時中、ナチスにより強制収容所に送られた体験を、精神分析を交えて書かれていたものですが、近いうちにガス室に送られることがわかっている人の行動や、ところどころ目を背けたくなるようなナチス側の人の行動などが書かれており、途中読むのをやめようかと思いう時もありましたが、気になって読み進めるのを繰り返した一冊でした。
本書の後半に(途中本文を略しています)
「この収容所は1944年のクリスマスと1945年の新年の間の週に、かつてないほど大量の死者を出したのだ。過酷さを増した労働条件からも、悪化した食糧事情からも、季節の変化からも、あるいは新たに広まった伝染病の疾患からも説明がつかない。むしろこの大量死の原因は、多くの被収容者がクリスマスには家に帰れるという、ありきたりの素朴な希望にすがっていたことに求められるというのだ。(略)強制収容所の人間を精神的に奮い立たせるには、まず未来に目的を持たせなければならなかった。(略)生きる目的を見いだせず、生きる内実を失い、生きていても何もならないと考え、自分が存在することの意味をなくすとともに、がんばり抜く意味も失った人は痛ましかぎりだった。(略)彼らが口にするのは決まってこんな言葉だ。「生きていることにもう何にも期待が持てない」
コロナ禍で生活の様式や習慣、楽しみ、外出が制限された今年と、収容所での極限状態であった人たちを比較や同じように見たりするのは根本的な部分で、大間違いなのは十分承知、また読み方が「浅い」、後半の「生きる事を書いた部分を読み解け」など指摘は多いと思われますが。
普段「なんとなく理解、説得させていた」、「なんとなく本人の意向を聞かずに遮断していた」自分の行動や発言に反省している状況です。
コロナ禍でも高齢者住宅の制限されている生活の中で少人数が集まって「活路」を見出している方もいれば(さすが!人生の先輩、色々と知恵を絞って行動に移す入居者がここには多いのだと感じています)、「早くお迎えに来て欲しいよ」という方もいます。
後者に対して私自身、スーパーマンでも神様でもないので何かしらの「答え」や「正解」など提案提示することはできませんが、少しの時間同じ方向性で生きる、耳を傾けて一緒に「解決策」を考える事で役に立つ職種でありたいと思っています。
居宅支援事業所 匿名